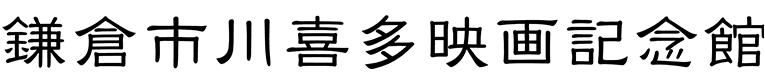企画展に足を運ぶ前に、ATGについてちょっとだけ詳しくなっておこう②~ATGが生んだ日本映画~
皆さま、こんにちは。気温がだいぶ高くなり、初夏の陽気を感じるようになりました。
記念館裏の庭園ではツツジの時期が終わり、草花が青々と茂っています。
(せめて写真でお楽しみください。)

企画展関連コラム、第1回ではATG設立の背景として、外国映画の輸入・配給を巡る戦後の映画界の状況と、そんな中でアートシアターを作りたいという志から生まれたATGの初期の活動についてご紹介しましたが、第2回のテーマは「ATGが生んだ日本映画」です。
1960年代半ば、日本映画界はどのような状況にあったでしょうか?
映画館の入場者数が史上最多を記録した1958年をピークに、60年代に入るとテレビの普及とともに映画界は緩やかな衰退期を迎えます。
しかし依然として映画は「娯楽の王様」であり、石原裕次郎や小林旭、高倉健、勝新太郎といったスターたちの活躍を、映画館の熱気とともに享受する時代が続いていました。
よく知られているように、日本では東宝・松竹・大映・日活・東映といった大手の映画会社が、専属の監督や俳優、スタッフを抱えながら、それぞれの特徴を活かした映画作りでしのぎを削っていました。
「撮影所システム」と呼ばれる確固とした産業があったおかげで、毎週のように新作が封切られ、業界自体は安定していた一方で、システムからはみ出した映画作りが困難だったのも事実です。
作品をヒットさせ、安定した収益を得ることが至上命題である映画会社のもとでは、一度成功を収めると、監督も俳優もそれを繰り返すことを求められ、個人としての挑戦や野心の実現は高いハードルとなっていました。
また、巷の映画館はそのほとんどが大手映画会社の系列館であり、各劇場ではほぼ自動的に上映作品が決まる仕組みになっていました。そのため、映画会社に属さない作り手は、作品を上映してくれる劇場を探すのも一苦労でした。

黒木和雄『とべない沈黙』(中央は主演の加賀まり子)
初期ATGの上映作品を見ると、ヨーロッパ映画中心のラインナップの中に、『おとし穴』(勅使河原宏)『みんなわが子』(家城巳代治)『人間』(新藤兼人)『彼女と彼』(羽仁進)といった日本映画が散見されます。
これらの監督たちは、実験的なドキュメンタリーを作っていた勅使河原、戦後のレッドパージや己の作家性を貫くためにそれぞれ松竹を退社した家城と新藤、岩波映画でドキュメンタリーを中心に活動していた羽仁と立場は様々だったものの、いずれも大手の会社に属さず、自身の独立プロなどで活動していました。
ATGはその初期から、通常の配給網からはみ出した日本映画上映の受け皿としても機能していたのです。

三島由紀夫『憂国』
そして1964年、外国映画の輸入自由化が実現したことで、「外国の芸術映画の紹介」という当初の役目をある程度果たし、その在り方を再び模索し始めたATGにとって大きな分岐点となったのが、三島由紀夫の『憂国』でした。
二・二六事件で決起した仲間と勅命の間で苦悩し、妻とともに切腹を遂げる軍人を描いたこの映画は、三島が自身の原作をもとに製作・監督・脚色・美術・出演をすべてこなした30分の短篇作品です。後に“三島のその後を暗示する”とも言われた本作ですが、1966年にATGで『小間使の日記』とセットで上映されたところ、内容・形式のセンセーショナルさもあって、かつてない大ヒットを記録したのです。
『憂国』の成功を目の当たりにし、日本映画の自主製作に乗り出すことになったATGが採った方法が「一千万円映画」というシステムでした。これは通常の劇映画の製作費が5~6千万円だった時代に、1本あたりの製作費を1千万とし、ATGと監督側で半額ずつ負担するというものでした。
予算としては厳しかったものの、ATG側は内容に関して一切口を出さないという条件だったため、作り手にとっては自らの作家性を存分に発揮するチャンスとなり、また低予算ならではの工夫によって、これまでにない斬新な表現が次々と生まれました。この共同製作の仕組みによってATGは、日本映画史上に残る数多くの傑作を残すことになったのです

大島渚『儀式』
ATGで作品を発表した作家たちは、1960年前後に“松竹ヌーヴェルヴァーグ”として注目を集め、その後独立プロを興した大島渚(『絞死刑』『少年』『儀式』等)、吉田喜重(『煉獄エロイカ』『戒厳令』等)、篠田正浩(『心中天網島』『卑弥呼』)をはじめ、映画会社での仕事で既に評価を確立していた岡本喜八(『肉弾』)、市川崑(『股旅』)、増村保造(『音楽』)といった存在が中心ではありましたが、ATGの何よりの特徴はその「越境性」にあったと言えます。

吉田喜重『エロス+虐殺』
(大正時代と現代が交錯する)

篠田正浩『心中天網島』
(人形浄瑠璃のように映画の中に登場する黒子)
ドキュメンタリー出身の松本俊夫(『薔薇の葬列』)や黒木和雄(『竜馬暗殺』)、テレビ界からは実相寺昭雄(『無常』)や田原総一朗(『あらかじめ失われた恋人たちよ』)、演劇界を牽引していた寺山修司(『書を捨てよ町へ出よう』)や唐十郎(『任俠外伝 玄界灘』)など、ジャンルを超えて作り手が集まったからこそ、映画作りの約束事に囚われない先鋭的な作品が数多く生まれたのです。

黒木和雄『竜馬暗殺』
(製作費を集めるため、黒木らスタッフが出入りしていた新宿ゴールデン街でもカンパが行われたという)
文学界の巨匠・三島由紀夫が映画を製作したことに象徴されるように、1960年代は、あらゆる芸術においてジャンル横断的な交流が盛んな時代でした。
監督名だけでなく、ATG映画のスタッフ・キャストを眺めてみると、「この人がこんな形で関わっていたのか!」とびっくりする発見があるはずです。
そして撮影所システム崩壊後の1970年代後半以降は、若手の映画作家たちに作品製作の機会を積極的に与え、大森一樹『ヒポクラテスたち』や森田芳光『家族ゲーム』といった名作を生むなど、ATGは時代ごとの状況に見合った形で、日本映画の多様性を保持し続けたと言えるでしょう。

森田芳光『家族ゲーム』
次回のコラムでは、ATGの中心的存在でもあった「アートシアター新宿文化」を取り上げ、1960年代後半の「映画と新宿」の関わりをご紹介します。お楽しみに!(胡桃)