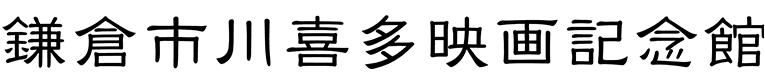小説家の山内マリコさんによるトークイベント「今ひとたびの〈あらくれ・お島・高峰秀子〉」を開催しました
ようやく冬の訪れを感じられる季節になりました。そんな11月のぽかぽかとした週末、当館では小説家の山内マリコさんによるトークイベント「今ひとたびの〈あらくれ・お島・高峰秀子〉」を開催しました。

『あらくれ』(1957年)は、監督:成瀬巳喜男×主演:高峰秀子の名コンビによる文芸大作です。いやなことを我慢せず、夫との喧嘩にも怯まず「やられたらやり返す」精神のヒロイン・お島が、男性遍歴を重ねながら時代の荒波を生き抜いていく物語で、高峰秀子が演じた役の中でもかなり強烈なキャラクターと言えます。公開当時は興行的にも作品評価の面でもあまり振るいませんでしたが、侍のような眉毛と口をへの字に結んだお島の逞しさは、現代を生きる女性たちに共鳴と喝采をもって受け入れられるのではないか、そんな思いから今改めて観ていただきたくプログラムしました。

小説家として数多くの著書を上梓されている山内マリコさんは、女性の生きづらさや女同士の友情(最近は”シスターフッド“という言葉もポピュラーになりました)など、フェミニズムの視点から数多くの文章を書かれています。大学で映画を専攻し、著作の中にもしばしば登場するなど映画への造詣が深いのはもちろん、高峰さんへの愛を公言されている山内さんに『あらくれ』について是非とも語っていただきたい!ということで、お忙しい合間を縫って鎌倉にお越しいただきました。

先月、書籍『きもの再入門』を出された山内さん、お島&高峰さんをイメージした会津木綿と伯母様譲りの羽織でご登場です。『あらくれ』でお島は着物選びが粋でない設定ですが、山内さんはとっても粋で素敵な着こなしですね。
富山市の出身でレンタルビデオ全盛期に映画と出会い、吉祥寺在住時に古い日本映画に目覚め、文学賞はとったけれど…なニート時代に、平日昼間の神保町シアターで高峰秀子主演の『放浪記』を観ようとしたところ、満席で入れなかったという経験から、ズブズブと日本映画の沼に入り込んでいった映画遍歴に始まり、高峰秀子(=デコちゃん)の女優としての魅力やキャリアの重ね方、名作出演における打率の高さなど切れ味あるトークが早くもさく裂です。

『あらくれ』が当時「成人映画」に指定されたことについて、山内さんはその背景には「(自分の妻に)こうなってもらっちゃあ困る」という男性たちの意図が透けて見えると指摘します。国会図書館で発見された当時の座談会の記事で、女流作家たちがお島を痛快だったと評する肯定的な声はもちろんあったものの、映画ひいては社会がいかに女性の生き方を規定し、あるべき女性をステレオタイプ化してきたかは明らかです。山内さんはご自身で「京マチ子映画の呪い」と呼んでいる、京マチ子が演じた強い女性キャラクターが映画の中で自分の人生を思い通りに生きようとすればするほど、死という罰(=結末)を与えられてしまう例を挙げながら、鋭く明快に分析してくださいました。
巨匠とされる監督においても、例えば溝口健二は作中でヒロインを徹底的に不幸にしていくのに対し、成瀬巳喜男は「女が強く生きていくというお話はお客が来てくれないんですね」と観客の嗜好を理解しつつも、女性を不幸にしている社会構造を映画を通して浮かび上がらせ、女性を不幸にすることで映画を面白くしようとしていない点において、成瀬作品は本当の意味で女性映画であるとの指摘は、映画史とフェミニズムに精通する山内さんだからこその分析でした。

あらゆる意味で男性に従属しなければいけなかった時代、脚本家・水木洋子と成瀬によって、自己主張する女性を肯定的に描いた『あらくれ』のラストは、土砂降りの中を着物の裾をまくし上げてお島が再び歩き出すというものです。安易なハッピーエンドでもしんみりした結末でもふんわりしたオープンエンドでもなく、観ている者すべてにすっきり、爽やかな印象を与えるというお話しに、客席からもたくさんの頷きをいただきました。

山内さんはベルギー出身の女性監督、シャンタル・アケルマンが1975年に発表した『ジャンヌ・ディールマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』が2022年、英国映画協会発行の映画雑誌『Sight and Sound』が10年に1度行うアンケート「史上最高の映画」で突如1位を獲得した例を挙げ、映画の評価は時代によって変わるものであると指摘されました。その意味で『あらくれ』もまた“早すぎた”映画であり、「今の時代の流れを加味して“傑作”ということにしましょう」と最後に力強い宣言もいただきました。
約1時間にわたる濃密なトークの中には、ご自身の結婚生活にも言及し「自分の人生の手綱を一瞬でも離してはいけない」という断固たるメッセージや、「いけいけお島」といったポップな応援ワード散りばめられ、たくさんのエネルギーを受け取ることができました。またテレビドラマ『おしん』に言及し、同じ時代を描いた作品であることから、実はおしんに近いところでお島もまた生きていたのではないか、おしんと同じようにお島も80年代頃まで元気に生きていたかもしれないといった、想像力が膨らむお話も印象的でした。

後日、トークに参加された男性のお客様より、「シャンタル・アケルマンという人のその映画を是非観てみたいと思った。徳田秋聲の原作も読んでみる気になった」というお言葉をいただき、とても嬉しい気持ちになったことも書き添えておきます。
山内マリコさん、素晴らしいお話をありがとうございました!