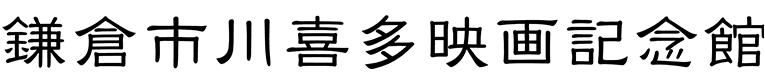トークイベントで振り返る企画展「BOWシリーズの全貌―没後30年 川喜多和子が愛した映画」
3月18日に開幕した企画展「BOWシリーズの全貌―没後30年 川喜多和子が愛した映画」は、約3か月の会期を無事に終えて、6月25日に終了しました。川喜多長政・かしこの長女である川喜多和子に初めて光を当てた今回の企画では、会期中、ゆかりのある方々にご登壇いただき、計3回のトークイベントを開催しました。トークイベントを通してこの3か月を振り返りたいと思います。
■4月15日:【特別上映】『ピクニック』『ラ・ジュテ』上映+トークイベント「川喜多和子は、映画の自由、自由の映画を求める者たちのジャンヌ・ダルクだった」
ゲスト:高崎俊夫さん(編集者/映画評論家)
開幕から約1ヵ月、トークイベントのトップバッターは編集者として数々の名著を世に送り出し、映画評論家としても活躍される高崎俊夫さんです。高崎さんは、1976年から始まったフランス映画社のBOWシリーズの中でも、特に初期の作品に思い入れが深いということで、和子が愛してやまなかったジャン・ルノワール監督の『ピクニック』(1977年公開)の上映に合わせてご登壇いただきました。
高崎さんは、80年代に「月刊イメージフォーラム」の編集者としてBOW作品を誌面で紹介し、フランス映画社配給作品の監督たちにインタビューを行うなど和子と直接交流を持ちつつ、同じ時代の空気を吸いながら併走されました。トークでは時代の流れを辿りながら和子の足跡を振り返ってくださいました。
欧州留学から帰国した和子は、黒澤明監督『悪い奴ほどよく眠る』(1960)の助監督を経て、次第に「映画を見せる」仕事へと移っていくのですが、その中で、スクリプターとして黒澤映画を支えていた野上照代さんと無二の親友になり、野上さんから紹介されて伊丹一三(十三)さんと知り合います。高崎さんは、野上さんが伊丹さんのお父様である伊丹万作監督の大ファンだったことから映画界へ入ったこと、1936年、川喜多長政が日本とドイツの合作映画として製作した『新しき土』で日本側の監督を伊丹万作が務めたことなど、川喜多家と伊丹家の縁が実は戦前から続いていたのだと感慨深く語られました。

1966年にジャン=リュック・ゴダール監督が初来日した際の裏話、和子が主宰していたシネクラブ研究会で起こった1968年の「鈴木清順監督問題共闘会議」、フランス映画社設立の経緯や大島渚作品の海外配給の詳細、フランス映画社のスタッフだった方が新宿に開いたバー「ジュテ」を舞台にした映画人同士の数々の交流etc.…まさに今回の展示の内容とリンクしつつ、さらに掘り下げる形で和子の生涯を辿ってくださいました。また和子との個人的な思い出もお話しいただいたのですが、高崎さんが「月刊イメージフォーラム」の編集部に入るいきさつにも和子が間接的に関わっていたというのは驚きでした。

今回の展示の冒頭で紹介した、大島渚監督が読んだ和子への弔辞の素晴らしさを教えてくださったのが高崎さんでした。大島渚監督という人は政治的で挑発的な発言が印象に残りやすい一方で、非常に情緒的で心優しい面もあるとかねてより考えていた高崎さんは、大島監督が遺した著作を丁寧に見直し、監督の抒情的な資質が垣間見られる文章を選んで1冊の書籍「わが封殺せしリリシズム」を編まれました。その際に、高崎さんが是非収録したいと思ったのが、この川喜多和子への弔辞だったそうです。
和子の生涯を語り尽くし、映画人たちにとって和子がどんな存在であったかを感動的かつ情熱的に綴ったこの弔辞は、展示全体の核になりました。高崎さんからご提案いただいたトークイベントのタイトル「川喜多和子は、映画の自由、自由の映画を求める者たちのジャンヌ・ダルクだった」も、大島監督の弔辞から引用したものです。トークの最後には、客席にいらっしゃった小山明子さんからもお言葉をいただき、和子さんとの知られざるエピソードをお話しいただきました。「わが封殺せしリリシズム」は小山さんにとってもお気に入りの1冊だそうです。
展示の準備から様々な形で今回の企画を助けてくださった高崎俊夫さん、本当にありがとうございました。
■6月13日:『夢みるように眠りたい』上映+アフタートーク
ゲスト:林海象監督
企画展「BOWシリーズの全貌―没後30年 川喜多和子が愛した映画」では、生前の和子と交流があった方々に、和子との思い出を綴ったメッセージをお寄せいただきました。当時の映画関係者は鬼籍に入られている方も多い中、池澤夏樹さん、野上照代さん、秦早穂子さん、戸田奈津子さん、富山加津江さん、小笠原正勝さん、工藤夕貴さん、ジム・ジャームッシュ監督、ヴィム・ヴェンダース監督、柳町光男監督、林海象監督と、そうそうたる方々にお忙しい中ご協力いただくことができました。
関連上映では主にBOWシリーズとして封切られた外国映画を上映したのですが、日本映画の海外への紹介も重要な仕事だったことをお伝えできればと、柳町光男監督『火まつり』と林海象監督『夢みるように眠りたい』の2作品は、英語字幕付きで上映を行いました。上映初日の13日、林監督からご提案をいただき、上映後にアフタートークが実現しました。

帽子にサングラス、赤地に花柄のシャツと短パンという個性溢れる出で立ちで現れた林監督、まるでご自身の映画のキャラクターのようなカッコ良さです。それまでまったく映画や撮影の経験がないところから、この映画を作り上げたというから驚きです。トークでは、ご自身の映画のルーツから、映画を作ろうと思った入り口、鈴木清順監督作品をはじめ多くの作品を手がける映画美術の巨匠・木村威夫氏や、主演の佐野史郎さんとの出会い、ロケーション撮影の裏話(浅草の仁丹塔は外観も内部もすべてロケだそうです。映画の撮影後に残念ながら取り壊しになりました)、月島桜を演じた深水藤子さんと山中貞雄監督の関係など、こちらの聞きたいことには何でも、丁寧にお答えくださいました。本作に登場する日本映画最初の女優の役は、なんと原節子さんにもオファーしたそうですが、丁重にお断りのお返事があったとのことです。そして川喜多和子については、何者でもなかった自分に「この映画、海外に持って行こう」と声をかけてくれた、何でも話せるお姉さん、和子さんがいなければ今こうしてここにはいないだろうと話してくださいました。

急遽決定したトークだったため、広報する時間が限られていたにもかかわらず、当日は多くのお客様にお越しいただきました。質疑応答もたいへん盛り上がり、林監督がサインにも快く応じてくださったため、パンフレットとクリアファイルの物販は即完売し、皆さま監督との会話を楽しんだり、並んで写真におさまったり、ご満足いただけたようで何よりでした。
監督はどんな映画がお好きですかという質問に、鈴木清順では『東京流れ者』、黒澤明や深作欣二、キューブリック、ロバート・アルドリッチなど「ドライ」な映画が好きだと仰っていたのが、「私立探偵 濱マイク」シリーズなど監督の作品を思い出してもとても腑に落ちるものがあり印象的でした。ふらっと現れて、終わるとふらっと帰っていかれた監督。夏には、「濱マイク」シリーズの30周年を記念した4Kデジタルリマスター上映を控え、来年頃には新作にも取り掛かりたいと仰っていました。ますますのご活躍を楽しみにしています。
■6月3日→6月24日:【特別上映】『東京画』上映+トークイベント「フランス映画社での仕事、川喜多和子という人」
ゲスト:森遊机さん(映画研究家/書籍編集者)、齋藤敦子さん(映画評論家)
4月の高崎俊夫さんのトークが、フランス映画社の「外側」からの視点だとすると、「内側」からの視点でもお話をお聞きしたいと開催したのが、かつて同社に在籍していた森遊机さん、齋藤敦子さんのお二人によるトークイベントです。昨年秋に開催した特別展「映画をデザインする―小津安二郎と市川崑の美学」の関連イベントとして、市川崑研究の第一人者である森さんにご登壇いただいた際に、かつてフランス映画社の社員だったことを知り、その時にお客様として来てくださった齋藤さんも元同僚とのことで、この機会にお二人でお話しいただきたいと思ったのがそもそものきっかけでした。
フランス映画社で1983年から90年まで宣伝を担当していた森さんと、1984年から89年宣伝や字幕翻訳を担当していた齋藤さん。入社のきっかけ、お互いの印象に続いて、かつて同社が入っていた銀座5丁目・大日ビルの外観や通路、郵便受け、エレベーターなど森さんご自身が後年に撮影した写真を見ながら、当時の仕事ぶりを思い起こしていただきました。写真を見て齋藤さんは「こんな写真わざわざ撮る社員はいない」とひと言。先日のイベントでの再会は約30年ぶりだそうですが、元同僚という関係性だけあって、お互いに遠慮がなく、とても息の合った掛け合いでした。また、森さんが描いたオフィスの見取り図で、当時の社内レイアウトや各社員の座席の位置なども判明。社長の柴田駿さん、副社長で宣伝部長の川喜多和子をはじめ、個性豊かなスタッフが揃っていたフランス映画社。会社を辞めた後も、皆さんそれぞれが映画界を支えて活躍されていることを思うと、多くの人材を育てた場所だったことがわかります。


当時はテレックスからFAXへの移行期で、まだまだほとんどの作業がアナログだった時代、宣材写真を35㎜の本編フィルムから1コマ1コマ時間をかけて抜き(森さんの記憶では、『グッドモーニング・バビロン!』のメイン写真のコマのチョイスは齋藤さんの労作と和子が語っていたそうです)、初日プレゼント用ポストカードなどのノベルティ作りを工夫し(森さん作成の『ストレンジャー・ザン・パラダイス』の黒くて丸い缶バッジはマスコミやファンに好評だったとか)、1本の映画がお客さんに届くまでには、配給会社の方たちの膨大な作業を経ていることを痛感しました。
森さんと齋藤さんが在籍していたのはフランス映画社の黄金時代と言ってもいい時期です。何気なくお二人の口から出る名前の豪華なこと。ヴィム(・ヴェンダース)は茶豆とコカ・コーラが好物だった、池波正太郎さんは絶対に試写に遅れることがなかった、淀川長治さんが齋藤さんにつけられたあだ名の話、黒澤明監督『乱』の準備で時間があるからと書いたエッセイ(『父へのレクイエム』のち『母べえ』に改題)が文学賞をとってしまった野上(照代)さん、その受賞パーティーで野上さんへの応援歌として、TVアニメ『巨人の星』主題歌の替え歌「行け行けノンちゃん」の合唱の音頭をとった大島(渚)監督、ジム(・ジャームッシュ)、武満(徹)さん……他では聞けないこぼれ話の連続に、場内は何度も沸き立ちました。
川喜多和子についても、その人柄が見えるエピソードをたくさんお話しいただきました。ニットのプルオーバーにジーンズという軽装で、ロゴのないエルメスのショルダーバッグを肩にひっさげて街を走り回っていた和子のアクティブさ、大皿料理で人をもてなすのが大好き、魯山人の食器を窯ごと買うなど、贅沢を贅沢と思わない育ちの良さ、一方で忙しい試写の合間には牛丼やラーメン、サンドイッチなどで手早く昼食を済ませたり、コロッケパンはいいけど焼きそばパンは許せないというこだわりぶり。日本のアニメはわからないと言いながらも『ルパン三世 カリオストロの城』だけは初公開当時から認めて人に薦め、その後の宮崎駿作品は公開初日に駆けつけていたことなどなど……。
和子の早すぎた死を振り返りながら、お二人にしか語れない貴重なお話を惜しみなく披露してくださいました。最後にご提供いただいた当時のパンフレットやノベルティを抽選で10名様にプレゼントし、大盛況のうちにトークは終了しました。

このイベントは6月3日に実施予定だったのですが、前日の荒天により急遽中止となり、6月24日に振替開催となりました。皆さまには多大なるご迷惑をおかけしましたが、こうして会期末に開催でき、満員御礼で無事に締めくくることができて本当に良かったと思います。森さん、齋藤さん、ありがとうございました。
多くの方に支えられ、企画展「BOWシリーズの全貌―没後30年 川喜多和子が愛した映画」を完走することができました。ご協力いただいた皆さま、ご来館いただいた皆さま、本当にありがとうございました。