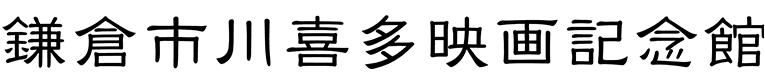企画展に足を運ぶ前に、ATGについてちょっとだけ詳しくなっておこう④~日本の映画ポスター史の転換点~、そして…企画展開幕!
皆さんこんにちは。
緊急事態宣言の解除によって少しずつ、日常を取り戻す動きが活発になってきました。当館も3か月の臨時休館を経て、6月2日(火)より無事に開館することができました!
なお、6月14日までの予定だった企画展「映画ポスターの革命〜ATGの挑戦〜」は、9月6日(日)まで延長して開催いたします。
まだしばらくの間は、県をまたいだ移動の自粛や、ソーシャルディスタンス確保のための入館者人数の制限といった不自由さが続きますが、それでも、ようやく企画展を皆さまにご覧いただけることを、まずは素直に喜びたいと思います。

企画展コラムの最終回は、今回の展示のメインテーマである「ATGの映画ポスター」に焦点を当てます。展示の導入としてご一読いただけますと幸いです。
これまでの3回のコラムを通して、ATGが1960年代という時代と分かちがたく結びついていたことが見えてきたかと思いますが、ATGの「ポスター」もまた、この時代と密接に関係していました。
さらにATGのポスターは、映画ポスターの歴史において大きな転換をもたらしたという点でも、非常に重要な存在です。
今回のコラムでは、「時代性」と「映画ポスターの転換」という両面から、ATGのポスターをご紹介していきましょう。
ATGのポスターは、大きく2つに分類することができます。「グラフィックデザイナー」が手がけたものと、「映画ポスターデザイナー」が手がけたものです。
今でこそ広く認知され、需要も多いグラフィックデザイナーですが、かつては「商業デザイナー」「図案家」と呼ばれ、その芸術性や作家性が評価されるよりも、職人的な仕事として捉えられていました。
昨年秋から冬にかけて開催した特別展「明治・大正文藝シネマ浪漫」でご紹介した、三越の広告で知られる杉浦非水も、大正から昭和にかけてのグラフィックデザインの黎明期に活躍した「図案家」でした。

しかし、1951年に日本宣伝美術協会(日宣美)が設立され、53年から作品公募を開始すると、日宣美は新人デザイナーの登竜門として才気あふれる若手デザイナーを次々と輩出、グラフィックデザインが注目を集めるようになっていきます。
この時代を席捲したデザイナーに粟津潔、宇野亞喜良、横尾忠則、和田誠といった人物がいます。
土着的な思想に基づき変幻自在な作品を展開する粟津潔、独特な姿態の少女絵で時代を超えてファンを獲得し続ける宇野亞喜良、唯一無二の色彩感覚と前近代的な嗜好を持った横尾忠則、書籍や雑誌の装幀をはじめ、ユーモラスなイラストでお茶の間にも浸透している和田誠…




イラストレーターとしても独自の存在感を放つ彼らの作品は、「シルクスクリーン」という印刷技術の普及で、コストを下げた少量印刷が可能になった状況を背景に、当時活発な展開を見せていた“アングラ演劇”においても注目を浴びていました。
第2回・3回のコラムにもあるように、あらゆる芸術ジャンルの混淆が特徴的だったこの時代、ATG映画もそれを上映していた新宿という街にも、「映画」や「演劇」といった明確な境界はなく、ATGならではの自由度と芸術性への志向の中で、演劇ポスターの担い手が映画ポスターを手がけたことは、時代の必然だったと言えるでしょう。
このようにATGのポスターは、グラフィックデザインの興隆やアングラ演劇ポスターとの重なりを背景に、新進気鋭のアーティストたちによって支えられた側面がある一方で、映画の草創期から脈々と続いてきた「映画ポスター」の流れにおいても重要な意味を持つものでした。
商業的なメディアである映画においては、映画ポスターもまた、主演スターを中心とした出演者の配置、刺激的な惹句の挿入など、表現という点では今も昔も多くの制約を伴っています。戦前のロシアや革命後のキューバ、戦後の東欧など社会主義・共産主義国で花開いた、純粋芸術としての映画ポスターを例外として、一般的に映画ポスターは「宣伝」という大いなる目的に奉仕するものとして認知されてきました。
映画ポスターのデザイナーたちは多くの場合、映画会社の宣伝部社員であったり、会社と専属契約を結んでおり、ポスターにデザイナーの名前が刻まれることは稀でした。商業美術と呼ばれた時代のように、職人的な仕事として捉えられていたのです。
日本の映画ポスターの歴史を辿っていくと、松竹モダニズムを担った河野鷹思や、ヨーロッパ映画の薫り高さをポスターに描き出した東和の野口久光など、時代を超えて名を残すデザイナーは散見されるものの、基本的にはその匿名性ゆえ、映画ポスターを支えてきたデザイナーたちはあまり知られていないのが現実です。
しかし、非商業的な映画を配給・製作し、何よりも芸術性・作家性を重んじたATGは、外部のグラフィックデザイナーだけでなく、業界内の映画ポスターデザイナーにとっても、限りなき自由と実験的な表現が可能な場となりました。
展示室を見回してみると、あるいは出品目録を眺めてみると、ATGで最も多くのポスターを手がけているのは、「大島弘義」「檜垣紀六」「小笠原正勝」という3人のデザイナーであることがわかります。
もしかしたら、彼らの名前を初めて目にする人も少なくないかもしれませんが、ATGの宣伝全般を請け負った「東宝アート・ビューロー」に所属していた彼らこそ、それぞれATGの「前期」「中期」「後期」のポスターを担い、誰よりもATGを支えた映画ポスターデザイナーたちなのです。
東和で野口久光のもと厳しい鍛錬を積んだ大島弘義は、『尼僧ヨアンナ』をはじめ、主に外国映画を上映していた初期のポスター数多くを手がけ、ATGというブランドをポスターの上でも確立しました。
外国映画の場合は、ポスターを作る時点で既に映画が完成していることもあり、必ず映画を見てからポスターに取り掛かるという野口の姿勢を受け継いだ大島もまた、映画から受けたインスピレーションを丁寧に、しかしポスターの掟を破る《黒》を多用して、大胆かつ実験的にポスター上に表現しました。


東宝の娯楽映画ポスターで鍛えられた檜垣紀六は、ATGが日本映画に深く関わるようになった頃から洋画・邦画のポスターデザインを手がけました。檜垣の主義は「映画を見ずにポスターを作ること」。ATGでの仕事を「純粋デザイン」と位置づけていた彼は、しばしば難解な映画の内容に囚われないデザインを目指しました。
檜垣のポスターを見ると、空間の使い方や色使い、スチル写真のアレンジなど、すべてが非常に大胆であることに驚かされます。この企画展では、現役で活躍している映画ポスターデザイナーの方たちに、“思わず唸ってしまう1枚”を選んでコメントをいただいているのですが、何人もの方が檜垣作品を選んでおり、時代を超えた牽引力をもっていることがわかります。


市川崑監督の『股旅』(1973年)を皮切りに、ATG後期のポスターデザインを手がけた小笠原正勝は、「映画が作られる過程に立ち会」ってきた稀有なデザイナーです。
脚本を読んでイメージを膨らませ、撮影現場では実際の撮影とは別に、ポスター用の写真を自ら撮影することもしばしばだったという小笠原は、なんと映画化決定前、原作者宅の訪問にも同行したことがあるそうです。
若手の育成という役割に重点を置いていた後期ATGにおいて、ポスターデザイナーである小笠原もまたスタッフの一員として、創造の現場を共にしていたのです。


このようにデザインに対する取り組み方はそれぞれですが、映画ポスターデザイナーとして数多の作品に携わってきた彼らのキャリアにおいて、ATGでの仕事は、映画ポスターの大きな可能性を示すものとなりました。
ちょうど今年4月には、ポスターデザイナーとしての小笠原の軌跡を振り返る書籍が出版され、檜垣の書籍も現在準備中など、彼らの仕事に対する注目は今後益々高まっていくことでしょう。
ATGの画期的な映画ポスターは、同時代のグラフィックデザインが注目を集めていた流れと、映画史の初期から脈々と続いてきた映画ポスターの流れがちょうど交錯し合ったところに誕生した、極めて特別な存在だったのです。(終り)(胡桃)