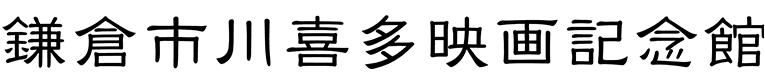企画展に足を運ぶ前に、ATGについてちょっとだけ詳しくなっておこう③~ATGの中心地「新宿」~
皆さん、こんにちは。
未だ開幕できていない企画展「映画ポスターの革命〜ATGの挑戦〜」について、展示とは別の角度からATGをご紹介するコラム、3回目はATGと「新宿」の濃密な関わりにスポットを当てます。
新宿という街は、渋谷や銀座、浅草などと並んで都内でも有数の盛り場ですが、いわゆる“団塊の世代”と呼ばれる年齢の方々にとっては、ある種特別な存在感を伴う地名ではないでしょうか。
樺美智子さんの死に象徴される1960年と、日米安保の自動延長の年であった1970年という2つの安保闘争に挟まれた1960年代は、体制に対する異議申し立てが世界各地で行われ、学生運動やベトナム反戦運動が吹き荒れた時代として知られています。
この時代は日本でも、ヘルメットとゲバ棒のスタイルで、日大・東大を中心とした大学紛争が全共闘運動として全国に広がり、佐藤栄作首相の外国訪問を阻止しようとした羽田での闘争や、成田空港建設をめぐる三里塚闘争など、戦後史に刻まれる数々の出来事が起きました。
その中にあって新宿は、1968年10月21日(国際反戦デーにあたる)に、デモ隊が新宿駅になだれ込んで、米軍のジェット燃料輸送を阻止しようとし機動隊と衝突した「新宿騒乱」や、ベ平連(ベトナムに平和を!市民連合)を中心とした、新宿西口地下広場における反戦フォーク集会など、まさにこの時代を象徴する場所だったと言えます。
※これらの歴史的出来事に関しては、本来なら写真や映像で見ていただくのが一番ですので、興味のある方は是非、下記サイトや検索システムをご活用ください。
新宿歴史博物館データベース「写真で見る新宿」:https://www.regasu-shinjuku.or.jp/photodb/index.html
中日映画社(サンプル映像の閲覧可):http://www.chunichieigasha.co.jp/
政治や歴史の舞台であっただけではなく、新宿はまた“カウンターカルチャー”“アングラ文化”といった若者文化の中心地でもありました。そして60年代半ばから後半にかけて花開いていく新宿を予見するかのように、1962年に誕生したのが「アートシアター新宿文化」でした。
1961年11月に設立されたATG(株式会社日本アート・シアター・ギルド)は、翌62年4月20日より、新宿文化劇場・日劇文化劇場・後楽園アートシアターの3館で上映を開始し、その後、横浜・大阪・名古屋・京都・神戸・札幌の劇場にチェーン展開していきました。
ただし、半年後には早くも興行上の不振から後楽園と京都が外れるなど、“芸術映画の専門館”という一貫性を全国的に維持することは、実際にはかなり難しかったようです。
東京では、新宿(新宿文化)と有楽町(日劇文化)にATGの上映館があり、皆さんそれぞれに贔屓や思い入れがあるかと思います。ですが、ATGの象徴と言えばやはり「新宿文化劇場(アートセンター新宿文化)」の存在を挙げるべきではないでしょうか。
その理由として、当時を体験していない私にとっては文献資料の多さもさることながら、次の3点を考えてみました。
①新宿文化の支配人であった、葛井欣士郎氏の存在
②映画館としてだけでなく、演劇の上演など文化的発信地としての役割
③ATG映画の中に映り込む当時の新宿
①新宿文化の支配人、葛井欣士郎
新宿文化は、新宿のランドマークの一つである百貨店、伊勢丹と明治通りを挟んだ向かい側に位置していました。劇場自体は解体されてしまいましたが、現在は「新宿文化ビル」となり、シネマート新宿や角川シネマ新宿といった映画館が入っています。

現在の新宿文化ビル(外観)
ATGの設立と同時にこの劇場の支配人に就任したのが、葛井欣士郎です。

写真中央が葛井氏
葛井はまず、これまでとは全く違った劇場を作るべく、「黒」をテーマカラーにしたシックな内装や、ゆったりとした客席、サロンのようなロビーなど、様々な仕掛けを施してアートシアターとしての差別化を図りました。

劇場の外にあるウィンドウには、上映作品のスチル写真を看板にして飾り、終了後は会員向けに安く販売したという。写真はジャン=リュック・ゴダール『立派な詐欺師』(日本公開は1966年)のスチル看板(友の会会員より提供)
葛井は、日本映画の製作期においては作品の企画立案から携わり、数多くの名作を世に送り出しました。「消えた劇場 アートシアター新宿文化」(1986、創隆社)「遺言 アートシアター新宿文化」(2008、河出書房)などの著書を読むと、ATGの立役者としての葛井の存在と、それ故の新宿文化の重要性が浮かび上がってきます。
②文化的発信地としての役割
新宿文化の支配人として葛井が行なったのは、映画の上映だけではありませんでした。元々演劇熱の高かった葛井は、文学座の内部分裂による新劇団の立ち上げをきっかけに、1963年6月より、映画上映の終わった夜9時半から夜間の演劇公演を始めます。
当時、新宿にはまだ新劇の土壌がないと言われていましたが、紀伊国屋ビルの竣工とともに1964年紀伊国屋ホールが誕生、唐十郎《状況劇場》、鈴木忠志・別役実らの《早稲田小劇場》、寺山修司《天井桟敷》、蜷川幸雄《現代人劇場》といった小劇団が次々と旗揚げされて、「小劇場運動」と呼ばれる時代を迎えます。

現在の紀伊国屋ビル(外観)
彼らの多くが新宿文化で公演を行い、また近くの花園神社では唐十郎らが紅テントを張って公演するなど、演劇は劇場の中だけでなく、新宿という街に地続きに広がっていきました。
こうした中、1967年には新宿文化の地下に、三島由紀夫によって「蝎(さそり)座/シアター・スコーピオ」と命名された地下小劇場がオープンしました。規模の小さな劇場空間を得たことで、映画上映・演劇公演ともに更なる実験的・前衛的な内容への試みが可能となり、また会員制のバーとしても活用して、文化人たちのサロンとしての機能も果たしました。

蝎座入口
映画だけでなく演劇の発信地として、連日深夜まで賑わっていた新宿文化の周囲には、ゴーゴースナックやジャズ喫茶、飲み屋が乱立し、多くの若者やヒッピーたちが貪るように文化を享受し、時代を呼吸していたのです。
③ATG映画の中の「新宿」
前回のコラムで、ATGの日本映画は非常に少ない予算で製作されていた由のことを書きましたが、そのための工夫の一つに、セットを作る予算がかからない「ロケーション撮影」が挙げられます。
その撮影場所として、映画に頻繁に登場したのが「新宿」でした。
その筆頭は、なんといっても大島渚『新宿泥棒日記』(1969)でしょう。
時代に対して鋭い感性を持った大島監督は、この時代最も刺激に満ちていた新宿を舞台に、これまた時代を象徴する人気を誇っていた横尾忠則と唐十郎を起用して、虚構と現実が混じり合った不思議な映画を撮りました。
本作では、冒頭から新宿駅東口の広場で街頭パフォーマンスが展開し、紀伊国屋書店での撮影では同社社長が登場、花園神社の紅テント芝居を経て、最後は新宿騒乱の始まりを映し出して終わります。
唐十郎が歌う「新宿見たけりゃ 今見ておきゃれ」の言葉通り、この時代の新宿をそのままフィルムに焼き付けた作品として名を残しています。

『新宿泥棒日記』冒頭
他にも、吉田喜重『エロス+虐殺』(1970)では、新宿西口の副都心開発以前に広がっていた広大な浄水場の跡地が使われたり、松本俊夫『薔薇の葬列』(1969)では、新宿を庭のように闊歩するゲイボーイたちや、ゲリラ的に行われていた前衛パフォーマンスなど、新宿はごく自然に、いくつものATG映画の中に映り込んでいたのです。
ATGの中心地としての新宿はしかし、1974年の年末に公開された寺山修司『田園に死す』で終焉を迎えることとなります。同作品をもって、新宿文化はATG専門館ではなくなってしまうのです。ATGの映画製作はその後も1992年まで続けられますが、新宿文化の離脱によって、ATGのひとつの時代が終わったことは確かでしょう。
奇しくも、1972年初頭の連合赤軍によるあさま山荘事件を境に、学生運動も陰りを見せ、新宿を中心とした若者文化は、次第に渋谷へと移っていきました。
新宿文化にとって最後のATG作品となった『田園に死す』のラストでは、突然セットの壁が壊れ、恐山にいたはずの登場人物の背後に新宿の街が広がっているという演出がなされています。
撮影のために目の前で突飛な光景が繰り広げられようとも、びくりともしない新宿を行き交う人々。ATG映画の中の新宿が、映画と現実を奇妙に両立し得たのは、新宿という街そのものが大きな大きな劇場だったからなのかもしれません。

『田園に死す』ラスト
以上、今回は「新宿」という街からATGとその時代を眺めてみました。
「新宿とATG」というテーマは、個人的な思い入れが強いこともあり、やや感傷的な内容になってしまったかもしれません。長文に最後までお付き合いいただきありがとうございました。
次回は、そろそろ緊急事態宣言の終りも見えてきた様子なので、展示のメインでもある「映画ポスター」についてご紹介する予定です。(胡桃)