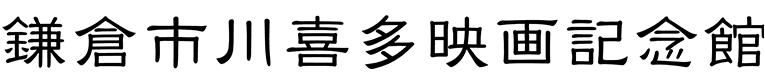企画展「昭和を彩る女優たち 松竹大船撮影所物語」②
梅雨入りを迎え、鎌倉も紫陽花が咲き誇る季節となりました。鎌倉と紫陽花といえば山田洋次監督の『男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋』(1982)を思い浮かべます。今年はゆったりと紫陽花を楽しむには大変なことが多いですが、映画を見るとマドンナ役のいしだあゆみ演じるかがりと寅さん、満男のデートがなんとも微笑ましく、気持ちに自然と余裕が生まれてきます。会期半ばで終了しました企画展「昭和を彩る女優たち 松竹大船撮影所物語」を紹介するコラムの第2回目となります。今回は前回紹介しきれなかった展示資料をご紹介します。
1931年、松竹は日本初の本格的トーキー映画『マダムと女房』(五所平之助監督)を公開し、日本映画はサイレントからトーキーへ変革の時代を迎えました。トーキーは同時録音で撮影するため、蒲田撮影所周辺の騒音が問題となり、静かな環境とトーキー設備を完備した撮影所への移転が必要となりました。そこで、候補地の一つにあがったのが大船でした。東京から1時間ほどで海や山が近くにあり、ロケーション撮影に適していること、また、大船田園都市の計画が中断され、未開発のまま残された土地があったことから、松竹は大船町(当時)の協力を得て、9万坪の土地に松竹映画都市を構想し、そのうち3万坪を撮影所として1936年に開設しました。当初は名称を松竹鎌倉撮影所にするという案もありましたが、「大船」の名を松竹映画が全国に轟かそうと「松竹大船撮影所」に決まり、町全体が松竹映画の拠点として“日本のハリウッド”のキャッチコピーで売り出されました。
トップスターとなった田中絹代から、モダンなスタイルで台頭していった桑野通子、高杉早苗、高峰三枝子といった新たなスターたちが活躍し、“女優王国 松竹大船”の名を全国に轟かせました。そして、多くの映画人が撮影所周辺に住まいを構え、大船は賑やかな街並みとなっていきました。


展示した1955年頃の撮影所界隈の絵は、当時、撮影所で働いていた方々からの聞き取りを元に鎌倉市中央図書館近代史資料室が中心となって作成しました。かつて撮影所周辺には多くの映画人の行きつけのお店がありました。小津安二郎監督は和食の「月ヶ瀬」、木下惠介監督、渋谷実監督は和食・割烹の「松尾食堂」、大庭秀雄監督、中村登監督、野村芳太郎監督は洋食の「ミカサ」といった監督たちが通ったお店の数々は松竹映画が生まれる創作の源にもなったといえます。現在も蕎麦処の「浅野屋」、中華の「でぶそば」では、撮影所の映画人たちが愛した食事を味わうことができます。大船駅前にある宝飾品・時計・眼鏡専門のコロナ堂も、撮影所とゆかりが深く、店内の奥にある大時計は、かつて松竹映画のセットで活躍した名脇役でもありました。



展示したサイン入りの大福帳は昭和24年から昭和25年にかけてのもので、「高峰三枝子」「佐野周二」「美空ひばり」といったスターたちの直筆サインを見ることができます。なかには「小津安二郎作“晩春” 曽宮周吉……笠智衆 昭和二十四年 七月」と記された一枚もあります。小津組の名優、笠智衆によって書かれたものでした。『晩春』(1949)は今年生誕100年を迎える原節子が、小津監督作品に初めて出演した作品です。原節子が演じた紀子という役名から『晩春』(1949))『麦秋』(1951)『東京物語』(1953)は紀子三部作ともよばれています。世界的に知られる巨匠、小津安二郎監督は、北鎌倉に居を構えた松竹大船撮影所を代表する映画人です。また、小津組の撮影監督、厚田雄春は、『淑女は何を忘れたか』(1937)で撮影を担当して以降、松竹映画の小津作品すべてで撮影を務めた名キャメラマンでした。二人の仕事は、映画史に類を見ない長年にわたるコンビで成し遂げた偉業といえます。展示ケース内には、小津監督が撮影現場で愛用したピケ帽や白足袋、銀座天賞堂のケースに入った特製のストップウォッチ、また『秋刀魚の味』(1962)の使用台本や画コンテを展示しました。“小津調”を象徴するロー・ポジションで使用された三脚は、厚田雄春が特注したロケーション用のもので、小津監督が愛した赤を塗ったことから茹でた蟹のようにみえ、“カニ”の愛称で呼ばれていました。ドイツのヴィム・ヴェンダース監督が小津監督へのオマージュとして製作した『東京画』(1985)では、厚田雄春が当時の撮影現場を再現する姿を見ることができます。

1958年に日本映画の観客動員数がピークに達したことから、黄金時代は終わりを告げ、1960年代から新たな時代が始まったといえるでしょう。1960年代初頭には、『青春残酷物語』(1960)を発表した大島渚をはじめ、篠田正浩、吉田喜重といった松竹の若手監督が中心となった「松竹ヌーヴェルヴァーグ」が注目されます。1961年には、松本清張原作の『ゼロの焦点』が、監督・野村芳太郎、脚本・橋本忍、山田洋次、撮影・川又昻によるスタッフで制作されヒットを記録しました。1958年に『張込み』で野村芳太郎監督は松本清張作品を映画化して以降、多くの清張映画を世に送ります。1974年に、『ゼロの焦点』のスタッフが結集し誕生したのが日本映画史上の名作『砂の器』でした。原作は1960年から翌年にかけて連載されており、14年もの歳月をかけて映画化が実現した作品です。撮影監督の川又昻の代表作ともなりました。昨年、2019年に逝去された川又昻を偲び、追悼展示として『砂の器』で使用された撮影台本、画コンテ、撮影現場のスチル写真を展示しました。川又昻は1945年、松竹に入社し、その後、小津組につき、厚田雄春のもと『東京物語』などの撮影助手を務めました。撮影監督になってからは、大島渚監督作品をはじめ松竹ヌーヴェルヴァーグの斬新な映像を手掛けるとともに、松竹大船の巨匠・野村芳太郎監督とのコンビでも数々の名作を生みました。今年は野村芳太郎監督の生誕101年となり、それを記念して、ワイズ出版から『映画の匠 野村芳太郎』(野村芳太郎・著/小林淳、ワイズ出版編集部・編/野村芳樹・監修)が出版されました。また、株式会社ボイジャーから『キャメラを振り回した男 撮影監督・川又昻の仕事〈増補決定版〉』(川又武久・著)の電子書籍版も出版され、下記のリンクで購入することができます。
→https://store.voyager.co.jp/publication/9784862390691
こちらもぜひ合わせてお読みください。2冊とも貴重な資料満載の書籍となっています。

今年、2020年、松竹映画100周年を記念して製作される映画『キネマの神様』(2021年公開予定)を手がけている山田洋次監督は、1961年に『二階の他人』で監督デビューした松竹大船撮影所を代表する映画人です。1969年に『男はつらいよ』第1作が公開されてから50年目にあたる、昨年、2019年に、シリーズ50作目となる『男はつらいよ お帰り 寅さん』が公開され、劇場に足を運んだ方も多いことでしょう。日本を代表する女優たちがマドンナ役で登場する「男はつらいよ」シリーズは、“女優王国 松竹大船”を象徴する映画といえます。1936年、昭和11年に開設し、2000年、平成12年に閉鎖された松竹大船撮影所は、昭和という激動の時代を背景に、夢の工場として、多くのスターと映画を世に送りました。家族をモチーフに人と人とのつながりを温かく描いてきた“大船調”の作品群は、100周年を迎えた松竹映画に受け継がれ、これからも私たちに時代を越えて映画の魅力を与え続けてくれることでしょう。(文)