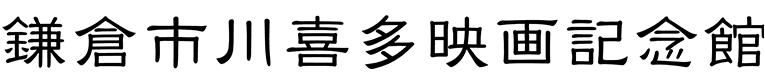企画展に足を運ぶ前に、ATGについてちょっとだけ詳しくなっておこう①~ATG創立までの日本の映画界事情~
こんにちは!大変ご無沙汰しております。外出自粛の日々の中、皆さまいかがお過ごしですか?
想定していなかった家での時間を有効に過ごせる人・なかなか上手く使えない人様々ですし、誰もが多かれ少なかれストレスを感じながら日々を送っているのではないかと思います。川喜多映画記念館でもスタッフ同士の接触機会を減らし、リモートワークを活用しながら、刻一刻と変わる状況の中、開館後のことを必死で考える日々です。
ただ、たとえ今は開館ができなくても、お客様と直接顔を合わせることができないとしても、記念館として発信をしていくことが大切だと考え、「記念館だより」にて、映画や記念館に関することをお伝えさせていただきます。
今回は、本来なら4月頭から開幕予定だった企画展「映画ポスターの革命―ATG(アート・シアター・ギルド)の革命―」に関連した内容を担当学芸員よりお届けします。企画展では「映画ポスター」をメインにご紹介するので、コラムでは展示内では詳しく触れられなかった、それ以外の視点から企画展を眺めてみたいと考えています。(全4回を予定)

「ATG」と聞いてもすぐにピンとくる人は正直少ないのではないでしょうか。ATGとは「アート・シアター・ギルド」という何やらカッコいい名前の略語なのですが、会社名であると同時に、「アート・シアター」いわゆる芸術映画を上映しよう!という映画界の連帯でもありました。

芸術映画を上映するために、なぜわざわざ連帯しなければならなかったのか?その背景には、戦後から1960年代初めの映画界の状況が大きく関わっていました。
川喜多長政が「東和商事」を設立し、1920年代後半からかしこと共にヨーロッパ映画の名作を買い付けて日本で公開する「配給」の仕事に従事していたことは、ご存知の方も多いかもしれません。 “米英鬼畜”のスローガンからもわかるように、太平洋戦争中は、アメリカをはじめとする連合国の映画を輸入し、観客がそれを見ることは許されていませんでした。
戦争が終わり、ようやく外国映画が自由に見られるという喜びもつかの間、GHQによる占領政策により映画の輸入業者は制限され、占領後も日本映画保護の目的も含めて、洋画の輸入本数を制限する「クオータ制」がとられるなど、依然として厳しい状況が続きました。
その後も配給会社ごとに輸入できる本数が決められる割り当ての制度や、前年度の実績によって割り当て本数が決まるといった事情から、配給会社は「作品の質」よりも「儲かるかどうか」を重視せざるを得なくなり、必然的にヨーロッパ映画よりもアメリカ映画の輸入が増えていきました。
1950年代後半にかけて日本では、娯楽性の高いハリウッド映画は見られても、芸術性の高いヨーロッパ映画を見る機会は次第に奪われていったのです。
実験精神に富み、意欲的な映像表現を持つ芸術的な外国映画を日本で紹介しにくいという実情に心を痛めた映画人たちの活動によって、1961年11月15日、株式会社日本アート・シアター・ギルドは発足しました。そして第1回作品に選ばれたポーランド映画『尼僧ヨアンナ』をはじめ、『オルフェの遺言』(フランス)、『野いちご』(スウェーデン)、『エレクトラ』(ギリシャ)、『長距離ランナーの孤独』(イギリス)など、初期の作品のほとんどがヨーロッパ映画で占められている点や、同時代の映画だけでなく1950年代半ばから後半に作られた作品が含まれている点も、戦後の配給業界の混乱と制限をめぐるこうした事情によるものでした。



1964年7月、ようやく外国映画の輸入自由化が実現したこともあって、ATGの役割は「芸術性の高い外国映画を紹介する」ことから「作家性の強い日本映画を製作する」ことへと次第に移行していきます。次回のコラムでは、ATGが製作した日本映画に焦点を当ててご紹介したいと思います。お楽しみに!(胡桃)