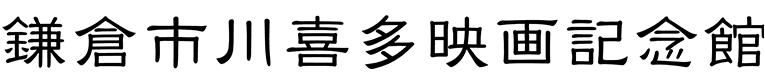フィリップ愛に染まった時間
企画展「ヨーロッパ映画紀行」関連上映にて、1月27日より3日間、ジェラール・フィリップが早世の画家モディリアーニを演じた『モンパルナスの灯』を上映しました。
1958年に公開された今作からわずか1年後、自らが演じたモディリアーニの生涯を辿るかのように、ジェラール・フィリップ自身、36歳の若さでこの世を去っています。
そんな不思議な運命をもつ作品の上映に合わせて、28日(土)には、日本でジェラール・フィリップ映画祭を企画し、日本で再びジェラール・フィリップ(G・P)を甦らせた、山中陽子さんをお迎えしてトークイベントを実施しました。

山中さんは20代はじめに、G・Pの魅力に取り憑かれ、G・Pの作品を上映しようと26歳の若さで映画配給会社セテラ・インターナショナルを設立、1996年より4回にわたって映画祭を開催しただけでなく、本の出版や、ファン同士を繋ぐファンクラブの立ち上げなど、様々な形でG・Pを現代に甦らせた方です。
日本でG・Pを語る際には欠かせない存在ですが、一つの会社の社長さんであり、私はこれまでお会いしたことがありませんでした。若くして会社をつくり、並々ならぬ情熱で突き進んで来られた方ということで、どんな女傑がいらっしゃるのか…とやや戦々恐々としていたところ、約束の時間に現れたのは、若くて気品のある美しい女性でした…!

きりっとした美しさをたたえつつも、人当たりの柔らかい印象でほっとしながら、慣れない私の進行ながら、トークは終始和やかなムードに包まれました。
画面でG・Pの美しい写真をご覧いただきつつ(写真を選んでいるときの楽しかったこと!)、彼の代表作を年代順に辿りながら、作品にまつわるお話をお聞きしました。
年上の人妻に恋をする17歳の高校生を演じ、出世作となった『肉体の悪魔』(1947年)では、ヒロインの女優、ミシュリーヌ・プレールが「この役はG・Pでなければできない」と言い切って出演が決まったこと、G・Pの魅力が開花した重要な作品であるにも関わらず、権利関係が複雑で、長い間上映されてこなかったこと、その理由のひとつに、監督のクロード・オータン=ララが戦後数々の代表作を残しながらも、ヌーヴェル・ヴァーグの作家たちの登場によって、否定するべき旧世代の映画人として槍玉に挙げられ、自らの作品の上映を拒んできたこと。
ひとつの作品を巡る物語が、時にはとんでもなくドラマチックであることを実感したのでした。
今回のトークでは、G・Pというテーマと一緒に、「映画配給」の仕事についても伺いました。お客様の目にふれにくいながらも非常に重要なこの仕事は、川喜多夫妻が戦前から携わってきた仕事でもあり、機会があれば是非お客様にも知っていただきたいと考えていました。
G・Pの話に花が咲き、あまり踏み込むことはできませんでしたが、セテラさんがどのようなスタンスで作品を選び、どのような思いで私たちに映画を届けてくれているのかを、実際に配給した『クロワッサンで朝食を』を例に挙げながらお聞きすることができました。
「他の会社と競合するような作品はあえて選ばず、セテラじゃなきゃできない映画、そして自分の愛するヨーロッパの名作を届けたい。その作品を見ることで、人生が少し豊かになるような、そんな作品を選びたい。そして原題を単にカタカナにするのではなく、タイトルの意味が皆にちゃんと伝わるような邦題をつける。」
という山中さんの言葉からは、ビジネスの世界ではありながらも、良い映画を見つけて日本の観客に届ける、という配給の仕事に対する誇りと使命感が感じられました。
予定の時間を大幅に超えてしまった今回のトークイベントでしたが、G・Pという俳優の魅力や、映画配給の仕事について、皆さんが少しでも新しい何かを発見していただけましたら幸いです。
「ヨーロッパ映画紀行」はまだまだ続きますので、是非お待ちしております!(胡桃)